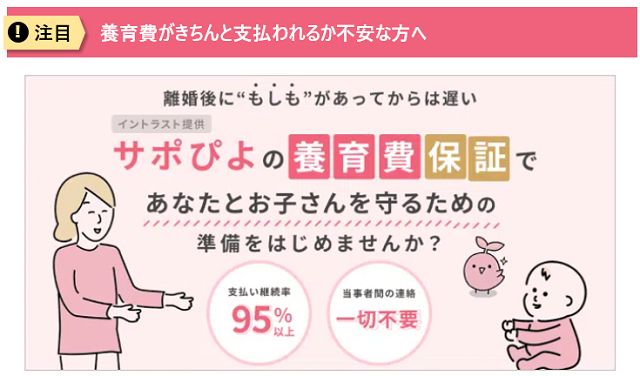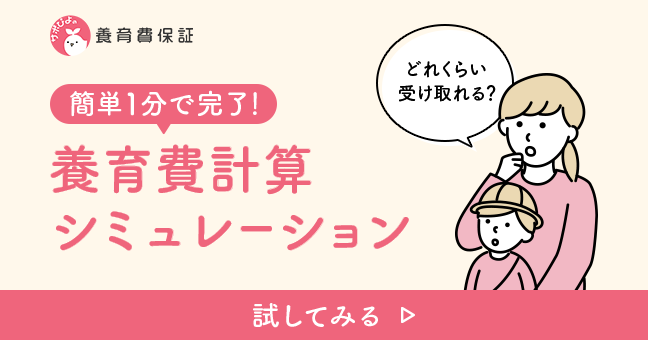更新日: 2023.01.27
公開日:2023.01.27
養育費はいつまで受け取れる?支払期間の考え方や例外を解説

離婚の際、子どもがいる場合は親権や養育費、面会交流など、取り決めることがたくさんあります。
中でも、今後の生活を考えたときに「養育費」はきちんと取り決めておきたいポイントの一つですが、いつまで支払われるべきものかご存知ですか?
この記事では、養育費はいつまで支払われるべきものなのか、またいつまで受け取るかを定めた期間を過ぎた後も受け取れるケースや、支払期間より前に受け取りが終了になるケースなどをご紹介します。
~ この記事の監修 ~

青野・平山法律事務所
弁護士 青野 悠
夫婦関係を解消する場合、財産分与・養育費など多くの問題が付随して発生しますので、これらの問題を全体的にみて、より望ましい解決になるよう尽力します。
1. 養育費は何歳まで支払義務があるのか

養育費とは「子どもの養育に必要とする費用」のことで、子どもと離れて暮らす親(非監護親)が子どもと一緒に暮らす親(監護親)に対して支払われます。
養育費はいつからいつまで受け取ることができるのでしょうか。一般的には、離婚が成立したときから成人年齢とされていた20歳までとするケースが多いです。
これは「非監護親は、子どもが成人に達するまで養育費を支払う義務がある」と考えられているためです。成人であれば、経済的に自立しひとりでも生計を立てられるようになる、という考えが元になっています。
とはいったものの、養育費をいつまで受け取れるかについて法律で定められているわけではありません。そのため、離婚をする親同士で話し合って自由に決めることができます。
- 子どもの進路
- 子どもが経済的に自立するタイミング
- 監護親が20歳以降の養育費の支払いを望んでいるか
などを考慮し、いつまで受け取るかを決めましょう。
ちなみに、子どもが2人いて満20歳まで養育費を受け取る約束になっているケースで、1人が20歳・1人が16歳など年齢差があった場合はどうなるのでしょうか。
この場合、上の子はすでに20歳になっているので養育費の支払いを受けることができなくなります。しかし、16歳の子はまだ20歳まで4年ありますので、その間は養育費の支払いが継続されるのです。
2. 成年年齢の引き下げはいつまで受け取れるかに影響する?

2022年4月1日から成年年齢を18歳へ引き下げる法律が施行されました。2022年4月1日時点で18~19歳の人は、この日より成年に達したことになります。この場合養育費はいつまで受け取ることができるのでしょうか?
2022年4月1日よりも前に「養育費の支払いは成人まで」と取り決めて離婚をした場合は、引き下げられる前の成年年齢(20歳)が適用されるため、養育費の支払期間は「子どもが20歳に達するまで」のままとなります。
特別な話し合いなどで取り決め内容が変更されない限り、取り決めた年齢までの支払義務が無くなることはありません。「成年年齢の引き下げの影響で、満18歳までしか養育費を受け取れない」ということにはならないので、安心ですね。
ただ、2022年4月1日以降に「養育費の支払いは成人まで」と取り決めて離婚をした場合は、引き下げられた成年年齢(18歳)が適用されます。この場合、養育費の支払期間は「子どもが18歳に達するまで」になるため注意が必要です。
なお、高校卒業後も大学や短大、専門学校へ進学する子どもが多くいる現代において、成年年齢(18歳)の時点で経済的に自立している子どもはごく少数でしょう。
そのため、養育費をいつまで受け取れるかを「子どもが20歳を迎えるまで、また進学した際は22歳まで」と取り決める方が多いようです。
養育費の相場やいくら受け取れるのかを知りたい場合は、こちらの記事を参考にしてください。
(参考)養育費の相場ってどれくらい?年収や子どもの人数別にご紹介|SiN
3. いつまでと決めた期日の後も支払いが継続するケース

養育費は、あくまでも「子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるもの」です。
そのため「子どもが成年になっても経済的に未成熟であれば、養育費の支払いは継続されるべき」と考えられます。ここでは、支払期間が継続するケースをご紹介します。
3-1. 大学や短大、専門学校などに進学した場合
4年制大学に進学した場合、20歳になった時点ではまだ学生で経済的な自立をしているとは言えません。
そのため、両親がお互いに合意すれば、大学卒業(22歳の3月)まで養育費の支払いが継続されるケースも少なくはないのです。この場合、両親の話し合いで合意すれば問題なく養育費の支払いが継続されます。
しかし、養育費を支払う側としては、少しでも額を減らしたいと考えるものです。合意しなかった場合は、家庭裁判所の調停で決めることになります。
親の学歴・職業・資力・子どもの希望と親の意向などを考慮した上で、大学進学へ進むほうが良いと判断された場合、養育費の支払い継続が決定します。
成年年齢の引き下げの問題もあるため、大学へ進むことを考えている場合は、養育費の受取期間を決めるときに「何歳の何月まで」と細かく決めておくほうが安心です。
3-2. 子どもが経済的な自立状態にない場合
子どもに障害や持病があったり闘病中である場合は、成人になっても働けないことがほとんどでしょう。この場合、子どもが経済的な自立をしている状況とは言えません。
子どもの心身の状況により経済的な自立が難しい場合は、成人後や20歳以降も養育費が支払われるケースがあります。
4. いつまでと決めた期日の前に支払いが終了するケース

非監護親には「子どもには非監護親と同じように暮らせる生活を保障しなければならない」という生活保持義務があります。 そのため、非監護親の生活に余裕がなかったり、失業や自己破産したとしても養育費の支払義務がなくなることはありません。
ですが、子どもが経済的に自立をしていれば、養育費の支払期間が終了する前に支払い終了、または減額が認められることがあります。ここでは、支払期間が継続するケースをご紹介します。
4-1. 子どもが就職した場合
公正証書に「満20歳まで」と記載されている場合、子どもが高校卒業後に就職したら養育費の支払いはどうなるか気になる人もいるのではないでしょうか。
子どもが高校卒業後に就職した場合、子ども自身が自分で収入を得るようになります。経済的に自立ができれば、親の扶養は必要ないと考えられ支払いが終了となるケースもあります。
20歳未満でも養育費の支払いが終わることもあるので、注意が必要です。なお、その場合は養育費の支払いは満18歳の3月までとなります。
しかし、就職をしたとしても、養育費を自動的に支払わなくてもよくなるわけではありません。
養育費の減額もしくは免除についても、監護親と非監護親が話し合って決めます。話し合いがまとまらない場合は、養育費減額もしくは免除の調停を申し立てて決めることになります。
なお、就職をしたとしても経済的に自立できていないと判断された場合は、養育費を引き続き支払い続ける必要があります。
4-2. 監護親の再婚相手と子どもが養子縁組をした場合
監護親が再婚し再婚相手と子どもが養子縁組をした場合は、子どもの第一次的な扶養義務は再婚相手になり、非監護親は二次的な扶養義務者となります。
この場合、非監護親の養育費が減額または免除されるケースがあります。養父からの経済的援助が見込まるため、子ども自身が経済的に自立をしていなくても減免が認められることがあるのです。
なお、以下のような場合には養育費を継続して支払う必要があります。
- 養親となった一次的な扶養義務者に十分な収入がない
- 監護親が再婚したが、再婚相手と子どもが養子縁組をしていない
5. 一度決めた養育費を変更する方法

養育費は、離婚時に両親の話し合いや家庭裁判所に調停や審判の申立をして、取り決めを行うことになります。
基本的には、取り決めた内容で支払い続けることになり内容が変更されることはありません。
しかし、状況によっては「いつまで支払うか」や「養育費の金額」などといった支払い約束の変更が、離婚後に認められる場合もあるのです。民法880条には「扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し」について記載されています。
「扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる」となっています。すなわち、養育費は状況に応じて変更することができます。
ただし、まずは両親で養育費の変更について話し合い、お互いに変更へ合意をすることが必要になります。話し合っても合意することができなければ、調停で話し合うことになります。
養育費の金額についても、支払っている間であれば何度でも変更を求めることが可能です。状況によっては、養育費の増額を求めることもできます。なお、失業などを理由に養育費の減額を相談されるケースもあります。
こういった場合、その都度、話し合いをして決めることになります。しかし、話し合いがまとまらなければ、養育費について最初に取り決めしたときのように調停・審判を行うことも可能です。
6. 養育費の支払いが止まるリスクを回避する方法

養育費は一括もしくは分割で支払うことになりますが、分割にした場合、支払う側の事情などで支払いが止まってしまうケースもあります。
滞納された場合、状況によっては生活にも影響がでるため、できるだけそうなることは避けたいものです。電話などで直接連絡をとって催促しても、きちんと支払ってもらえないことも少なくありません。
そこで、ここでは養育費の支払いが止まるリスクを回避するための方法について紹介します。
6-1. 公的証書に強制執行に関する文言を追加しておく
養育費の取り決めを記載した公的証書を作る際、「強制執行認諾文言」をあらかじめ追加しておくことは有効です。
この条項を追加しておくことで、家庭裁判所で調停をする必要がなくなります。「強制執行認諾文言」には裁判所を通さず、養育費の支払いをしてもらうために財産の差し押さえをできる効力があるのです。財産とは、給与や預貯金などをさします。
たとえば、養育費の支払いが遅れている旨を直接伝え、数日中に支払うと口約束しても支払ってもらえなかったとします。そういうときには、強制執行認諾文言が入った公正証書により、給与や預貯金などから滞納している分の養育費を支払わせることが可能です。
「強制執行認諾文言」がない場合や養育費について記載した公的証書自体がない場合、養育費の支払いが滞納していたとしても諦めてしまうケースが少なくありません。
本来ならば養育費は取り決めをしたものであり、必ず受け取れるものなので、諦めてしまうのはもったいないです。そうならないように、前もって対策しておくことは非常に重要です。
6-2. 養育費保証サービスの利用を検討する
養育費の支払いがストップするケースに備えて、「養育費保証」サービスの利用を考えるのも1つの方法です。
厚生労働省の調査によると、養育費を受けたことがない母子世帯は56%にものぼります。また、養育費の支払いを受けたことがあっても、途中で支払われなくなったケースが約39%となっています。
途中で支払われなくなる理由は、再婚による経済状況の変化や病気・リストラ、うっかり入金を忘れて、その後の催促がないとそのまま支払わなくなる場合などです。
未払いが発生したとき、養育費の支払いを催促したくても自分から元パートナーへの連絡はしにくいものです。養育費保証を利用していれば、最大12ヵ月分の養育費を立て替えてくれるので、養育費を受け取れなくなることがありません。
それに、立替金は保証会社の債権として回収するため、利用者が直接元パートナーに連絡をする必要がないのです。債権の回収に関しても無理な催促はせず、カウンセリングしつつ、支払いを促すといった流れになります。
養育費保証を利用するためには、公正証書や審判書・調停調書・離婚協議書や合意書など、養育費の取り決めをした書面の用意が必要です。
また、契約の際には事前審査がありますが、その後、契約書類の返送や、初回の保証料を支払うなど、1~2週間ほどで手続きは完了し、保証開始となります。
養育費の取り決めをしているにもかかわらず、離婚後に相手から支払いがなく約56%の方が受け取れていないという事実をご存じでしょうか?
イントラスト提供の「サポぴよの養育費保証」では、イントラストが支払人の連帯保証人となることで「立替え」と「督促」を実施いたします。
例え未払いが発生しても翌月すぐに立替えが受け取れて、また立替分はイントラストが支払人に督促するため、余計なストレスなどもなく安心。
現在、離婚手続きをしている方、今後養育費の未払いが心配な方はぜひ公式サイトをチェックしてみてください。
(まとめ)何歳まで払うか、子どものためにもきちんと取り決めよう
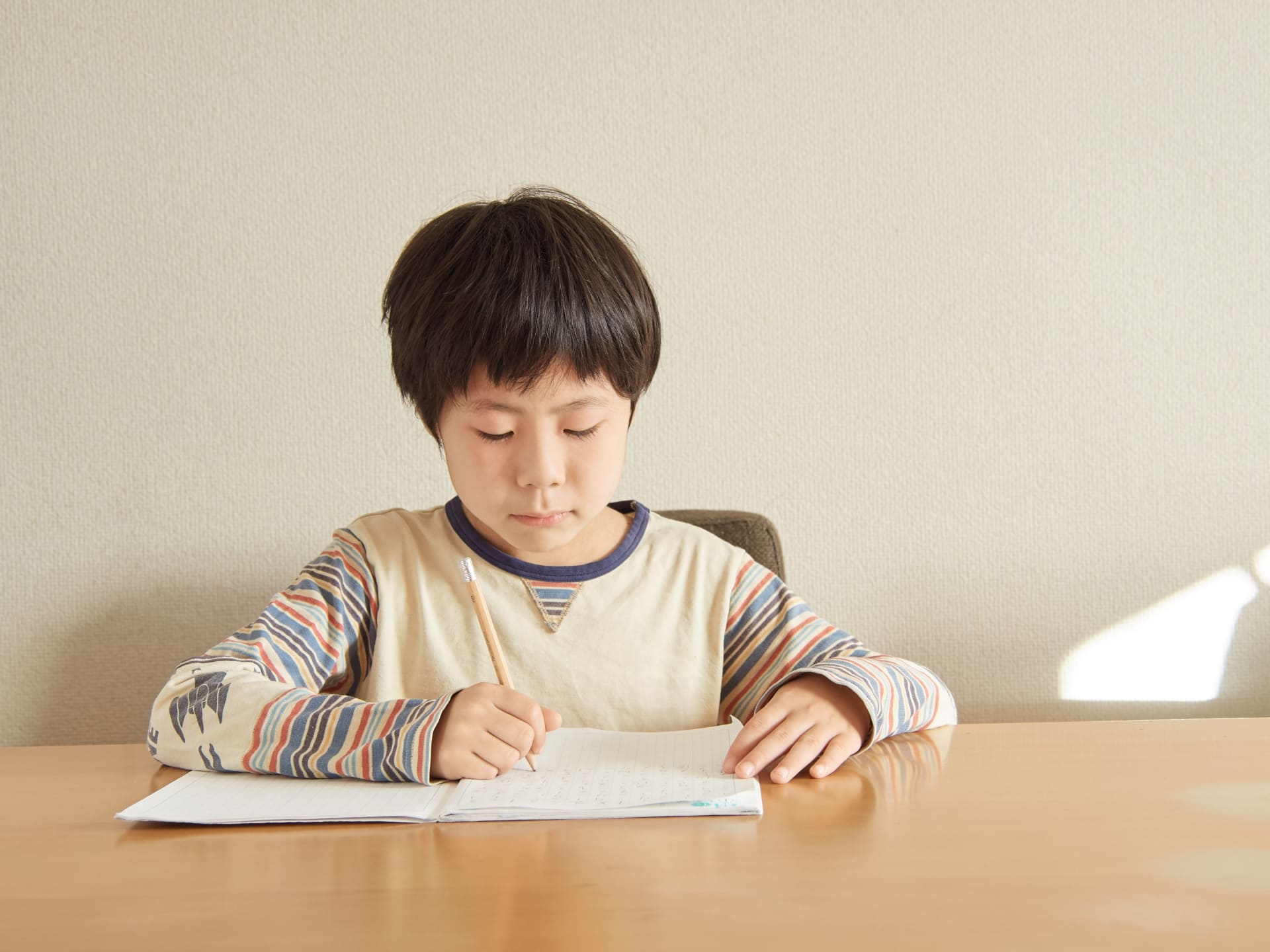
離婚の際に養育費について取り決めるときには、子どもの進路や子どもが社会に出て経済的に自立するタイミングを考慮し、支払期間をいつまでにするかを決めるようにしましょう。
また、毎月支払う約束をした場合に、養育費の支払いが途中でストップしてしまうケースもあります。養育費が未払いのまま請求せずに放置してしまうと時効が成立し、請求ができなくなってしまいます。
そのようなことが無いように、公正証書を作成するときは強制執行認諾文言を記載しすぐに強制執行ができるように備えるようにしましょう。
これから離婚をする場合や、まだ養育費の未払いが発生していない場合は、養育費保証が利用できます。養育費の未払い予防に、養育費保証サービスの利用もおすすめです。
<こんな記事もよく読まれています>